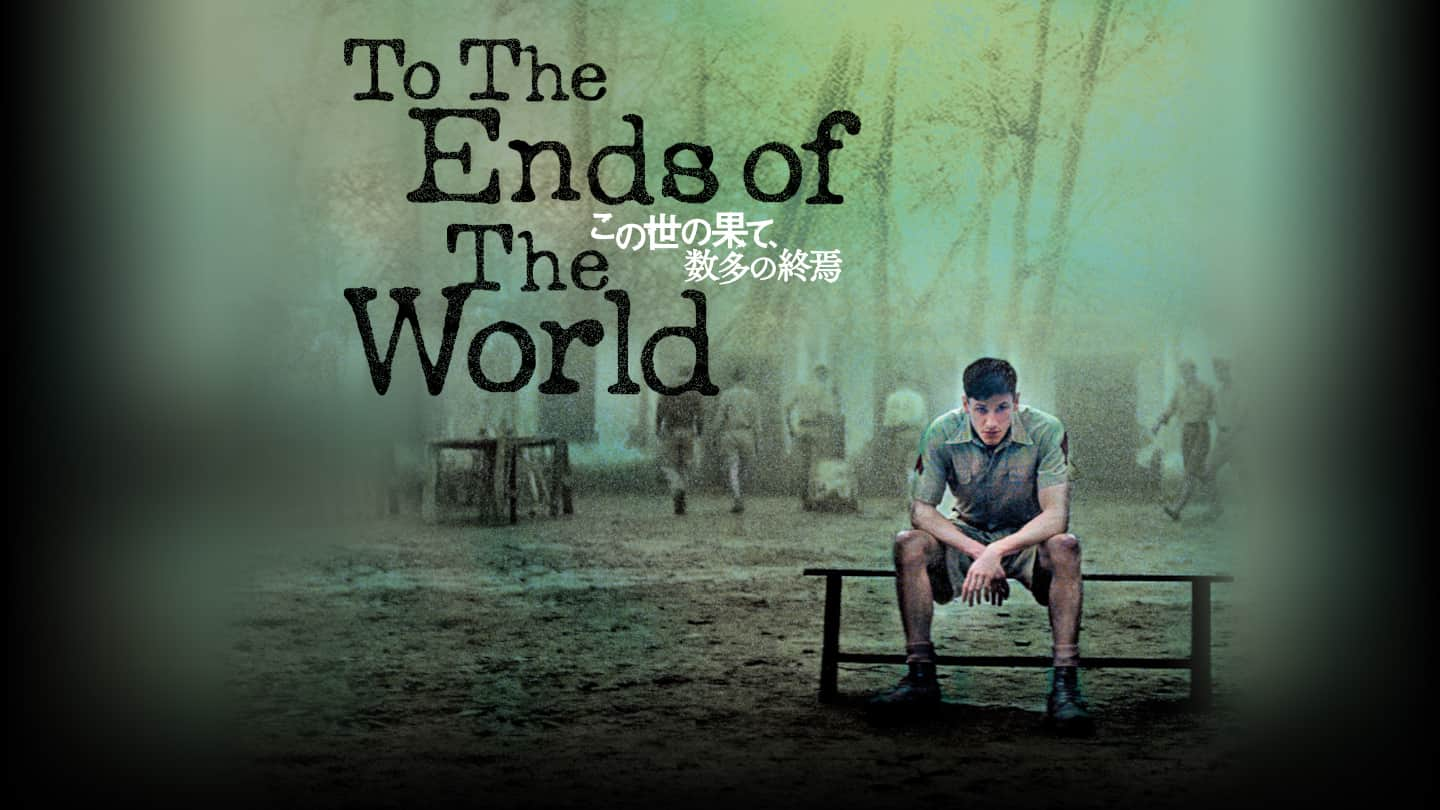フランス版地獄の黙示録なのだが…
この映画は、ギヨーム・ニクルー監督のユニークな発想でつくられたものなのか、あるいは単に映画づくりが下手なだけなのか(ペコリ)よくわからないところがあります。
日付を追って時間経過を示しながら物語として変化させられない構成、ぶっきらぼうな編集、戦場シーンに不釣り合いな音楽、そしてファーストシーンとラストシーンの意図不明な関連性、どれも違和感を感じるものばかりです。
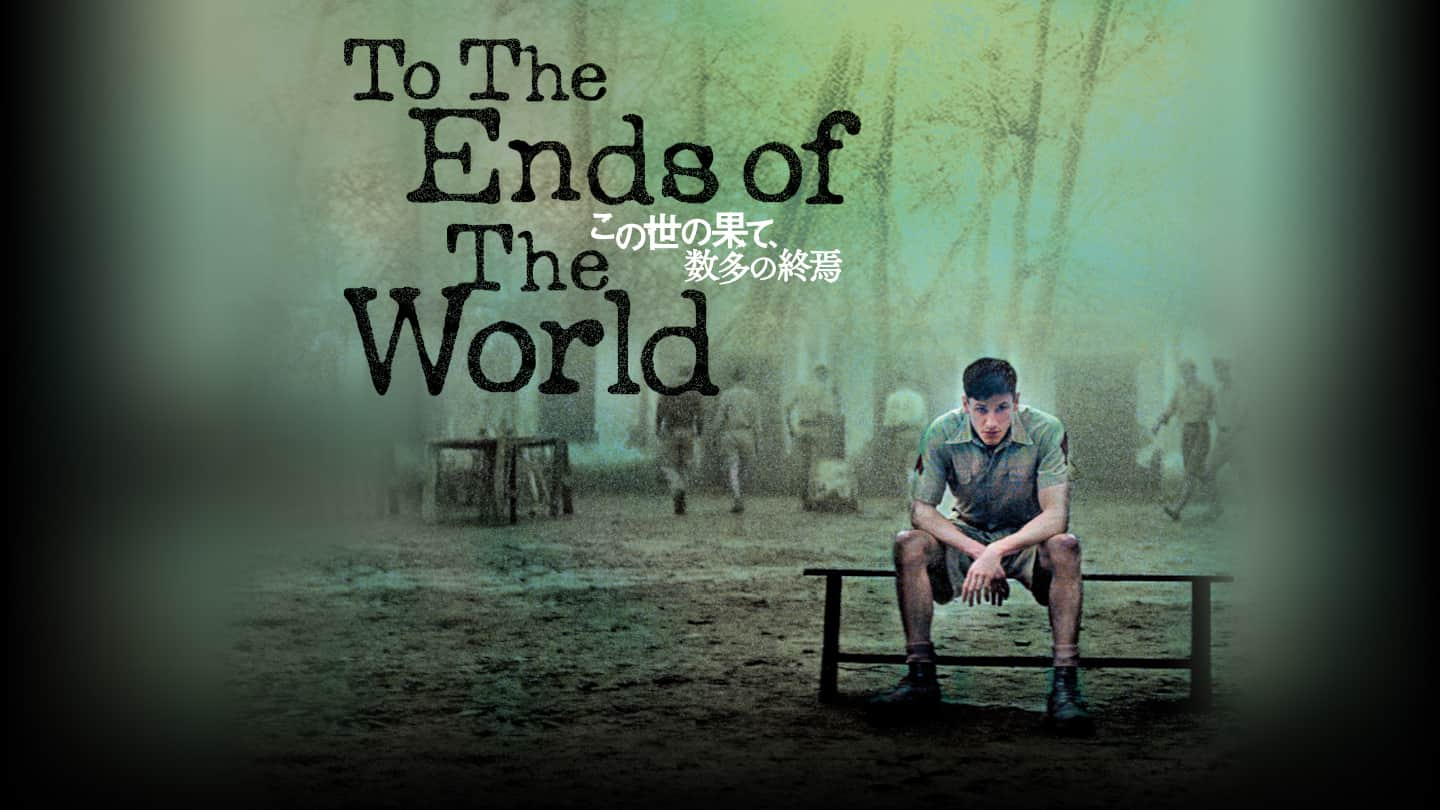
ギヨーム・ニクルー監督、日本での公開作品は1、2作ですが、IMDbを見ますと一観客が映画づくりが下手などと言うのはかなり失礼なキャリアです。年齢は1966年生まれですので現在54歳くらいです。
ですのでキャリア相応のユニークであるという視点で考えれば、映画そのものから感じることはないにしても、なにか見えてくることがあるかも知れません。
1966年生まれであれば、およそ100年続いたフランス帝国主義によるインドシナ統治も、インドシナ戦争も、そしてアメリカのベトナム戦争もリアルタイムでは知らない世代です。しかしながら映画人であれば(なくても)当然アメリカが描くベトナム(戦争)はよく知っているものと思われます。
そうした世代のフランス人がインドシナを題材に映画を撮ろうとした時、どういう視点があるのか、ギヨーム・ニクルー監督の答えがこの映画ということだと思います。
つまり、ベトナムの戦争をアメリカ的ベトナム戦争ではなく、インドシナ戦争というフランスの文脈で描こうとし、同じく戦場での狂気を「地獄の黙示録」的狂気ではなく、アウグスティヌス「告白」的懺悔として描こうとした映画ではないかということです。
物語の発端は斬新です。
ロベール(ギャスパー・ウリエル)が兄夫婦を惨殺されたことからベトミンのヴォー・ビン・イェン(ヴォー・グエン・ザップのこと?)への復讐に執念をもやすというのがこの映画の軸になっています。しかし、そのこと自体はロベールの口から語られるだけでまったく描かれていません。
さらに、ロベール自身が味わう苦難は日本軍による虐殺行為でありながら、その後一切日本軍は出てこず、ロベールの口から日本への憎しみが語られることもありません。そのロベールの体験と兄夫婦の虐殺の時間的関連も場所的関連も何もわかりません。
物語の発端についてはわからないことばかりなんですが、後に、なぜ日本人ではなくヴォー・ビン・イェンを恨むのかと聞かれ、黙って(笑って)見ていたからだと言い訳がましく説明しなくてはならなくなっている以上、斬新ではあっても基本的には失敗だとは思いますが、あえてそうした設定にせざるを得なかったと考えれば映画も少しわかりやすくなってきます。
なぜ、ヴォー・ビン・イェンへの憎しみを物語の発端とする必要があったのか?
この映画が描いているのは100年におよぶフランスの植民地支配に対するベトナム独立戦争です。しかし、宗主国フランスにとってみれば、それは仕掛けられた受け身の戦争です。都合がよいのではと思いますが、それがこの映画の立ち位置だということです。
ただ、この映画はそのことに対して無自覚というわけではなさそうです。
ヴォー・ビン・イェンへの復讐と言いながらその本人は登場もしませんし、そもそもの憎しみの源となる残虐行為そのものも存在したのかどうかさえはっきりしません。ロベールが言っているだけで何も示されません。ロベール自身にも憎しみが宿っているようにも見えません。
この映画にはロベールの戦うべき相手は登場しません。銃撃や死体という痕跡が示されるだけです。
何と戦っているのさえ見えないロベールの戦い、その意味では、7月、9月、12月と時は経過しても、敵はまったく見えず、ただひたすら密林を進むのみ、無残にも惨殺される死体は残されてもその行為は見えず、まるで何も進んでいないかのように、あるいは時が循環しているかのように見えるのは当然といえば当然です。
意識されているかどうかはわかりませんが、ロベールの一個人としての人物像がかなり曖昧に見えるのもそのあたりに理由があるように思います。おそらくロベールは一個人というよりもフランスのアイデンティティの象徴的存在であり、この映画はロベール=フランスの内省的な映画なんだと思います。
サントンジュ(ジェラール・ドパルデュー)という作家との関連でロベールを見ていけばそれが見えてきます。
サントンジュがロベールのもとに置き忘れるアウグスティヌスの「告白」、内容を知りませんのでいろいろググってみますと、要は「自分がこれまでの罪深く、道徳にはずれた人生を送ってきたことをどれだけ悔いているか(ウィキペディア)」を告白している懺悔録のような書物らしく、「その性的な罪についてもひどく悲しんでみせ、性的な道徳の重要さを強調」している箇所もあるとのことです。
また、サントンジュはロベールにフランスへ戻って幸せな家族を築けとも諭しています。
ロベールはインドシナにおけるフランスの暴力性とともに懺悔すべき罪の意識が宿っている存在ということでしょう。そしてその結果(身勝手ではあっても)自我分裂をおこし密林の中で発狂(自失状態)するのだと思います。
1946年のシーン、サントンジュが読む手紙(小説?)はその内容も誰にあてたものなのかも判然とせず、また曖昧にしか記憶できていないその時の印象だけですが、えらく第三者的にフランスの対インドシナを総括した上から目線のヨーロッパ中心主義的な内容だったように思います。
同じく、マイという存在にもそうした意識が見え隠れしているように感じます。子どもはロベールの子でしょうし、現在のマイはサントンジュの庇護下にあり、そして意味不明ですが医者から求婚されていました。マイはベトナムを象徴した存在にもみえます。
いまだ宗主国フランスの意識なのかも知れません。
冒頭とラストに繰り返されるロベールが椅子に座るシーンは、そのまま見れば、蛇に噛まれて亡くなる同僚が後ろを歩いていきますのでロベールが日本軍の虐殺から生還した時点と考えられますが、そうではなく、ロベルトは映画の結末としての発狂したロベルトであり、他の兵士たちが行き交う背景は幻影、あるいは別次元の映画的処理と考えるべきでしょう。逆転は狂気に閉じ込められたロベールの表現だと思います。
どのシーンだったか忘れましたが、ロベールが水中から顔を出すシーン、「地獄の黙示録」的でした。